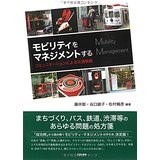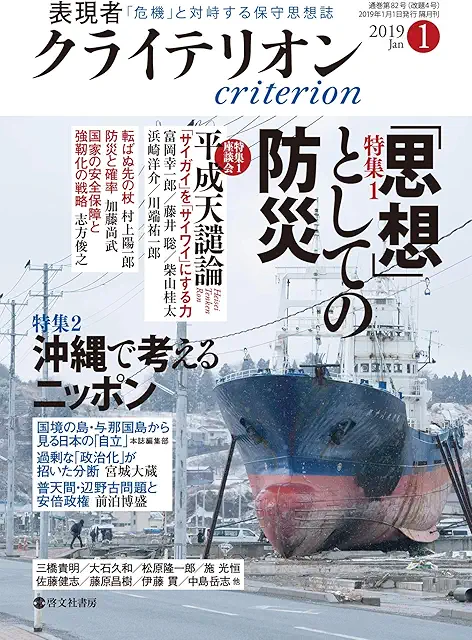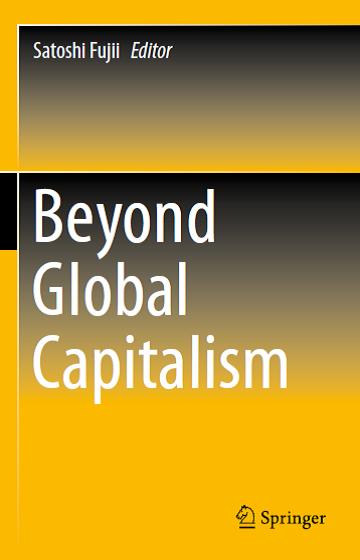都市社会工学専攻 交通マネジメント工学講座交通行動システム分野(藤井研究室)
研究室紹介ページ
- 研究室紹介ポスター:PDF(2025年 update)
- 研究室紹介ポスター:PDF
- 藤井先生から学生へのメッセージ:動画
- Introduction of Fujii laboratory (English ver.)
研究紹介のインタビュー記事
- 【京都大学大学院工学研究科 藤井聡教授】都市社会工学に関する学びをインタビュー(学びの地図 by 株式会社オンジン.2024年4月)
- 藤井聡に1日密着[京都大学大学院教授/元内閣官房参与](藤井聡チャンネル『表現者クライテリオン』.2023年11月)
- 持続可能なまちづくりのための交通行動システムに関する藤井聡教授の洞察(LIVIKA.2023年7月)
- 藤井聡・京大教授が語る“真の土木工学” 「僕の研究こそ、土木の本道だ!」(施工の神様.2019年8月)
「都市・交通・国家」の課題解決に向けた実践的社会科学
社会科学(social science)という学問は、もともとは近代化の過程で生じた様々な社会的課題に対峙するための「総合的」で「実践的」な知的活動でした。しかし近代の幕開けから 200 年以上が経過した現在、社会科学の「専門分化」が進んだ結果として、それらの知見を実際の問題解決に応用することが難しくなる傾向にあります。現実の社会問題は、それぞれが総合的な現象として存在しており、研究者の都合に合わせて「分化」してくれるわけではないためです。当研究室はこうした現状に鑑み、都市や地域、交通や国土計画をめぐる具体的な問題への対処法を考える上で、「社会や人間は総合的存在である」という理解を踏まえつつ、実践的な社会科学研究を推進しています。
研究概要
都市・交通における「社会的ジレンマ」の解決策に関する実践的社会科学研究
環境汚染、景観の劣化、交通渋滞、観光地の混雑など社会問する実践的研究題の多くは、「楽をしたい」「好きなことがしたい」という個人の利益が社会全体の利益と衝突する「社会的ジレンマ」によって引き起こされます。また、交通ネットワークや都市の構造に非効率な部分が残っていたり、新しい技術や制度の導入が遅れていたりという問題もあります。当研究室では、その背景にある社会的・心理的メカニズムや運用上の課題を把握し、より健全な都市と交通のあり方を模索する研究を行っています。具体的には、社会心理学の知見に基づく態度・行動変容手法の確立、クラウドソーシングデータを用いた交通・観光需要のモデリング、シェアードモビリティやマイクロモビリティの活用方法の提案などに取り組んでおり、方法論としては、統計データの解析や数理モデリングだけでなく、フィールドワークや事例研究、制度分析など、多様な手法を用いて総合的にアプローチしています。
市民社会の維持発展に必要な「精神」に関する社会心理学研究
都市や地域、さらには国家や世界の問題を解決する上で、現実に社会で生きている人々の「健全な精神的資質」が必要とされることは少なくありません。いくら法制度を整え、資金を集め、新しい技術を開発しても、それらを運用する「人間」に道徳性や倫理性、問題解決を目指す活力、冷静なバランス感覚などがある程度備わっていなければ、望ましい結果は得られないためです。しかしもちろん、「よき精神」「よき態度」「よき感覚」がどんなものであるかは簡単には定義できず、それらを獲得する方法も単純ではありません。そこで当研究室では、たとえば地域に対する愛着や宗教的情操が社会問題の解決を促し得るか否か、そして政治への無関心、ポリティカル・コレクトネスの過剰な追及、陰謀論の安易な受容などの具体的な問題の背後でどのような心理的メカニズムが働いているのかについて、実証的なデータを用いた基礎的な分析に取り組んでいます。
「ナショナル・レジリエンス」の強化に向けたマクロ経済政策及び国土計画論
都市や地域社会において豊かな文化的生活を営むことができるかどうかは、一国全体が十分な経済成長力や危機への対処能力を持っているかどうかに大きく左右されます。とりわけ現代においては、大規模な自然災害、金融危機、地政学的な緊張、少子高齢化などに備えて「ナショナル・レジリエンス」(国家規模の危機に対する強靭性)を確保することが喫緊の課題となっています。そのために当研究室では、防災を中心とする「国土強靭化」、成長力を高めるためのマクロ経済政策、国土の均衡を取り戻すための「東京一極集中」緩和策、「国土計画」と「防衛計画」の一体運用等について研究を進めています。また重要な研究成果については、国・自治体への提言や、一般のジャーナリズムや公開シンポジウムを通じた紹介にも積極的に取り組んでいます。
教育方針
本研究室では、以上の様な「環境づくり」の「進め方」についての様々な研究を進めていますが、
その展開にあたっては、以下の二つの点に留意しながら展開しています。第一に、「環境づくり」という目的のために必要な学術的枠組みや
知見があるなら研究分野の壁を一切考慮に入れずに知の探求を行うことが不可欠である、そして第二に、「実践」の徹底的追及の中にこそ最も
純粋な「知」の探求の動機を見いだすことができると同時に、徹底的に探求された「知」以上に実践に大きく貢献できるものなど無い、
したがって、「実践」と「学術」の無限の循環を可能な限り大きく、かつ強く展開することで、学術の深化と実践の高度化が同時に達成されていく
こととなる――この二つを前提に研究を進めることが、百年を上回る京大土木の実践と学術の伝統を継承する上で何よりも求められているの
では無いかと、考えています。今後も是非、本研究室の学術と実践の循環運動の力強さと大きさが確保され、拡大し続けているのかに、是非、ご関心をお向け頂けますと、大変有り難く存じます。
学生の研究成果等
当研究室の学生の研究成果や、当研究室の教員が行う授業の履修者のレポート等を、一部ご紹介します。
(授業レポートは、履修者の希望に応じて執筆者名を匿名やイニシャル等にしている場合がありますので、ご了承ください。)
- 水道民営化を日本で実施するべきか?(田角優弥、統合型科目「実践的人文・社会科学入門」2025年度レポート課題B)
- 四国新幹線の有効性について(冨嶋大晃、統合型科目「実践的人文・社会科学入門」2025年度レポート課題B)
- 東大生・京大生の就職先について(統合型科目「実践的人文・社会科学入門」2025年度レポート課題B)
- 日本における外国人受け入れ制限の提言(S.T.、統合型科目「実践的人文・社会科学入門」2025年度レポート課題B)
- 新型コロナワクチン接種と超過死亡の関係についての研究(分析方法及び分析結果の抜粋)(前田侑香、2024年度卒業論文:指導教授 藤井聡 より抜粋)